「早期発見すれば大丈夫」は言いすぎ。勝俣範之先生に聞く、ピンクリボン運動の功罪と「がんに勝つ」考え方の問題点
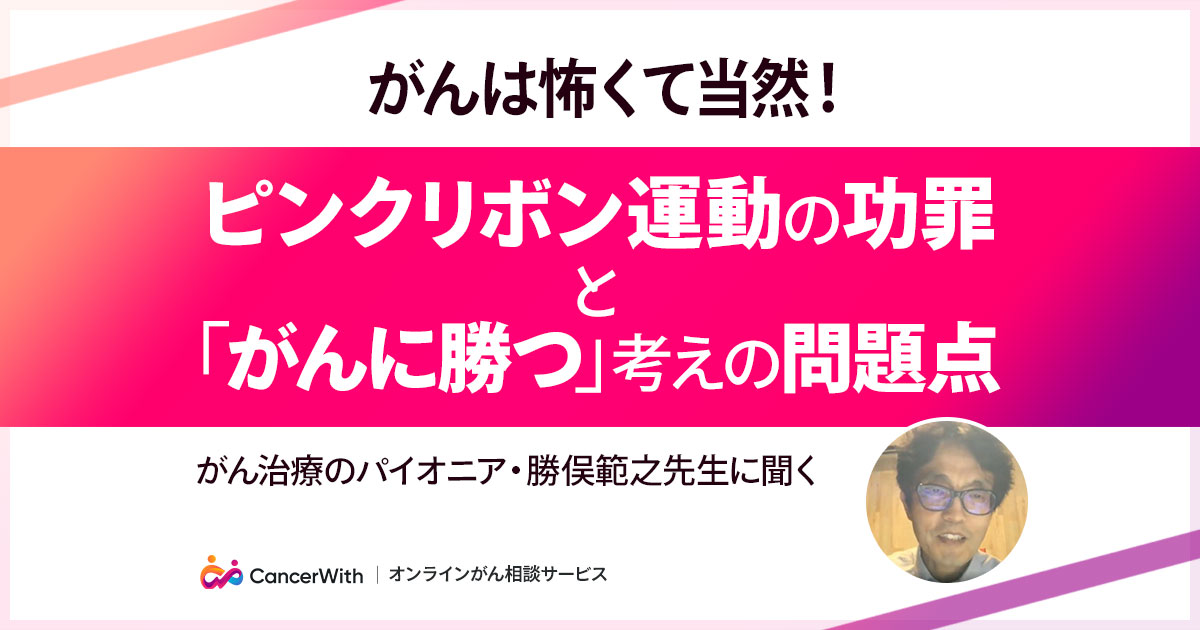
オンラインがん相談サービスCancerWithでは、ピンクリボン月間に合わせて「乳がん」をテーマにしたブログ記事を公開しています。今回は、CancerWithの顧問である腫瘍内科医の勝俣範之先生に「ピンクリボン運動の課題」を伺いました。
▼ 前回の対談
女性がん患者の離婚率は男性の6倍。勝俣範之先生に聞く、乳がん治療を続ける心得と患者の家族ができること
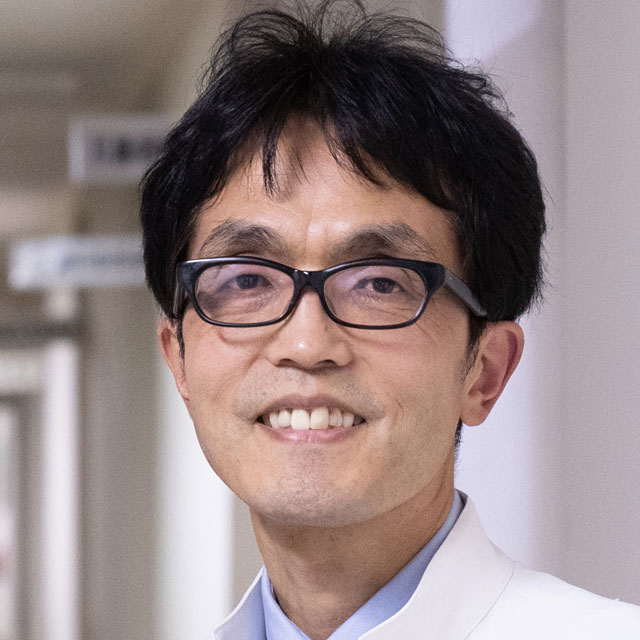
勝俣範之
日本医科大学 武蔵小杉病院 腫瘍内科 教授、部長、外来化学療法室 室長
株式会社ZINE / CancerWith 顧問

二宮みさき
CancerWithを運営する株式会社ZINE 取締役COO
2015年に乳がんに罹患、現在もホルモン療法を継続中
- 「早期発見」「早期治療」のみをアピールするピンクリボン運動の問題点
- 韓国では甲状腺がんの過剰診断問題も
- アメリカではがんになったことを隠す人はいない
- がんに勝つ/負ける マスコミの報じ方の問題
- がんを特別視する空気を変えたい
「早期発見」「早期治療」のみをアピールするピンクリボン運動の問題点
二宮みさき(以下、二宮)ピンクリボン運動の話をさせてください。「早期発見をすれば乳がんは怖くない」というようなフレーズのポスターを病院内などさまざまな場所で見かけます。私は乳がんの疑いがある中、診断がどうなるか分からない不安を抱えた状況でクリニックの院内で見かけました。ポスターは「早期発見すれば大丈夫」と謳っていましたが、逆に怖かった、という体験をしたことがあります。当事者になって調べてみると、確かに早期発見すれば予後も良いですし、生存率も高いのかな、ということが理解できたのですが、これってどう思いますか。
勝俣範之(以下、勝俣)そもそも医学的に言いますと、「早期発見すれば大丈夫」は言いすぎなんです。一部の人に至っては「乳がんは早期発見で撲滅できる」とまで主張している。それは言いすぎです。これは日本でのピンクリボン運動の大きな問題点だと思っています。
アメリカでピンクリボン運動が始まったときの趣旨を紐解いて行きますと、「早期発見」「早期治療」は謳っていませんでした。
オリジナルのピンクリボン運動が当初より掲げているのは「awareness」、つまり啓発でした。もともとは乳がんを理解し、患者を応援しようという、がん患者のための運動だったのです。
アウェアネス・リボン(英: Awareness ribbon)とは、輪状に折った短い一片のリボン、もしくはそれを描いた絵などで、アメリカ・カナダ・オーストラリア・イギリス、その他世界各地で、着用者(使用者)が社会運動、もしくは社会問題に対して、さりげない支援や賛同の声明を出す方法として使用されている。
アウェアネス・リボン(2021年10月1日 (金) 07:49UTC)ウィキペディア日本語版より
日本では「早期発見・早期治療」がうまくいっていなかったこともあり、ピンクリボン運動を輸入した際に「早期発見・早期治療」へとつなげようと考えたのでしょう。しかし、それは間違いだったと思います。私自身、「早期発見・早期治療」という言い方は止めてほしいとさえ思います。
もちろん早期発見で助かる患者さんもいますが、すべての患者さんが早期発見できるわけではありません。検診しても早期発見できない場合も多いです。早期発見、早期治療さえすれば乳がんはなくなってしまうような言い回しは良くありません。
例えば、ある患者さんは、半年前に乳がん検診をやったのに乳がんになったと言います。そのため、「検診で見落とされたんでしょうか」と聞かれることもあります。進行が早いがんでは検診を毎年していても、発見できないのです。つまり、検診には限界もあるのです。早期発見、早期治療をすれば良いとだけことさら喧伝し、がん患者さんを応援するメッセージを発しない日本のピンクリボン運動は非常に問題があると思っています。
韓国では甲状腺がんの過剰診断問題も
勝俣 世界的に見ても「早期発見、早期治療」を過剰に喧伝している国は日本以外にはどこもないんです。むしろ、現在は検診のデメリットが世界的にも問題になっています。「過剰診断問題」です。乳がんでも、検診で見つかるがんの3分の1は、治療をしなくても進行しないがんであることが指摘されました(出典:New Engl J Med 2012; 367: 1998-2005)。つまり、進行しないがんを早くみつけ、過剰な診断、過剰な治療を受けているだけの人がかなりいることが分かったのです。
過剰診断の問題は、甲状腺がんでも指摘されました。韓国が世界に先駆けて甲状腺がん検診を開始したところ、甲状腺がんがたくさん見つかりました。そして、その方たちの治療をされたのですが、甲状腺がんの死亡率はいっこうに下がりませんでした*1。
二宮 検診によってがんが過剰に見つかってしまい、治療する必要がなかった人まで治療していた、ということですね。
勝俣 そういうことです。検診にはメリットもあればデメリットもある、というのが世界的な認識です。ただやみくもに検診をすれば良いわけではありません。一番重要なのはがんを早く見つけることではなく、がんで命を落とさないことです。
早期発見が重要だと言いすぎた弊害も出ています。いざ、がんになった人に対して、「がんになったのは検診を怠ったから」「生活習慣も怠惰だったからだ」といった誤ったイメージ、レッテルがつきまとうことになってしまいました。
二宮 それは非常に分かります。幸い、私自身は差別されたことはないですが、「もしこの人にがんだと打ち明けたら何かネガティブなことを言われるかもしれない」とためらう場面はあります。
アメリカではがんになったことを隠す人はいない
勝俣 日本では勝ち組/負け組の二元論で語られがちですが、がんになるかならないかは勝ち負けではありません。がんになったからといって怠惰な人ではないですし、人生の落伍者でもありません。がんの多くは偶発的になるものなんですから。
日本とアメリカ、両国のがん患者の態度は全然違います。一番顕著に現れているのはブログです。アメリカのがん患者さんは、ブログを匿名では使いません。一方、日本のがん患者さんのブログはほとんど匿名です。
二宮 なるほど。確かにそうです。日本の闘病ブログの99%は匿名というイメージです。
勝俣 アメリカでは、がんになったことを隠す人はいません。ピンクリボン運動についても大きな違いがあります。アメリカでピンクリボン運動に参加したことがありますが、とてもにぎやかです。たくさんの患者さんたちがパレードで練り歩くんです。行き着いた会場にはステージがあり、患者さんたちが次々と登壇してマイクパフォーマンスしていくんです。中には抗がん剤の副作用で頭髪が抜け落ちた人もいます。壇上で患者さんが「私は乳がんと診断されたの! いま抗がん剤治療をしているわ!」と叫ぶと、会場で割れんばかりの拍手が起こっていました。
これは日本では考えられない光景です。アメリカと違い、日本のピンクリボン運動の現場では患者さんの姿を見かけません。患者さんが主役ではないんです。それはおかしいと思います。
偶発がんが半数以上を占めており、がんは誰でもなる病気。それなのに、日本では「がんはなった人に問題がある」という雰囲気があります。そうした雰囲気を変えることが、ピンクリボン運動の本来の存在意義だと考えています。「検診に行ったから大丈夫」と思っている人もいますが、それも危険です。明日は我が身なのですから。

がんに勝つ/負ける マスコミの報じ方の問題
二宮 「がんは怖い病気」というイメージがあります。私自身、がんと診断されてからは1週間くらい怖くて毎日泣きっぱなしで、何も手がつかない状態でした。少しずつ受け入れて治療を開始しましたが、多くの人がそういうプロセスを通ったと思います。なぜがんという病気は、そのように深く落ち込んでしまうのでしょうか。
勝俣 一つには、事実としてがんが死に至る病気だからです。怖くて当然です。
ただ、一方でマスコミの影響もあると思っています。がんの取り上げ方が極端なんです。マスコミは、「がんを克服した」か、「がんで壮絶な死を遂げた」という両極端な取り上げ方しかしません。
二宮 分かります。「がんに打ち克つ」とかも言いますよね。
勝俣 そうです。しかし、そもそも「克服」なんて言葉は実際の医療の現場では使われません。医学的には「勝った/負けた」なんて見解はないんです。では、がんになった人が負けなのか、がんで亡くなった人が負けなのか。そういうことではないんです。
がんに「勝ち/負け」はありませんし、5年経っても10年経っても、20年経っても再発する可能性はゼロになるものではありません。「克服した」なんて決して言い切れるものではない。がんは「克服する」ものでなくて、「共存するもの」であると考えてほしいと思います。
マスコミとしては、よりセンセーショナリズムに走ったほうが、視聴者や読者の注目を集めやすいのでしょう。そういう二元論のほうが扱いやすいんだと思います。でも、そろそろがんについて「勝ち/負け」で語ることはやめてほしいと思います。
おそらくマスコミとしては「共存」という言葉では面白くないんでしょうね。これまでもマスコミの関係者に対して「共存」という言葉を使うようにお願いしていますが、「面白くない」とはっきり言われたこともあります。
がんを特別視する空気を変えたい
二宮 がんについては、日本特有の空気感がある気がします。がん患者さんが自分らしく暮らすために、勝俣先生が社会に期待することはありますか。
勝俣 これまでも述べましたが、がんに対する世の中の考え方を変えたいです。「がんを克服する社会」ではなく、「がんと共存する社会」を目指すことができれば良いと思っています。
言ってしまえば、現在はまだがんを特別視しすぎているんです。誰もががんになるわけで、自分のこととして考えるべき。そして、がんになったとしても堂々と「私はがんですが何か?」と言えるようになれば良い。アメリカの職場では「私、乳がんになったのよ」と公言したら拍手を贈られるぐらいなんですから。
二宮 私も経験があって、以前、アメリカの知人を訪ねた際、言いづらかったけど「私はがんで」みたいに明かしたら、「すごいね」と拍手されて讃えられたんです。
勝俣 そうなんですよね。アメリカでは「偉いわね」「よくがんばってるわね」と讃えられるんです。日本では腫れ物に触るかのように、「かわいそうな人」として扱われてしまいますが、そこはアメリカを見習うべきなんです。
がん患者さんには、ご自身が悪いことをしたから、がんになったわけではありませんので、もっと堂々としてご自身を大切にしていってほしいと思います。また、社会は、がん患者さんを社会の負け組のようにレッテルを貼るのではなく、皆で応援、支援する社会にできればと思っています。
◆
10月はピンクリボン月間。CancerWithでは乳がん患者さんを応援しています
編集後記(仁田坂):
CancerWithの「With」も、「がんとの共存・共生」を意識したネーミングでした。僕が小学生だった1996年に大腸菌O157による食中毒が社会問題化。そのとき、「なんで体の中にあるはずの菌で人が死ぬんだろう」と疑問に思い、子どもなりにがんばって調べたところ、O157が「若くて人間との共生の仕方を知らない」大腸菌だということがわかった。それに対して、腸内にいる多くの菌たちは人間が死んでしまうと自分たちも生きられなくなってしまう。大腸菌の多くは時間をかけて人間との付き合い方を覚え、共存の道を選んでいることを知り感動しました。
今はがんで苦しんだり命を落としたりする人もいるかもしれませんが、がん細胞自体が人体との付き合い方を覚えていけば、腸内細菌のように、いつかはがんとも共生できるのではないか、とさえ考えています。克服が難しいからこそ折り合いを付け共生・共存していく。そんな意識でCancerWithとネーミングした経緯があります。これからもさまざまな方との対話を通じてがんとの共存方法を模索していきたいと考えています。
▼ 前回の対談
cancerwith.com
▼ ブレストアウェアネスについて
cancerwith.com
